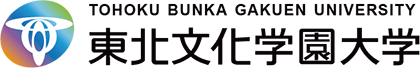わが愛しの作家たち
総合政策学部准教授 大野 朝子
中学時代から本格的に読書に目覚め、常に鞄のなかには文庫本を入れ、暇さえあれば読みふけっていた。夜に読書を始めると、つい熱中してしまい、いつのまにか部屋に朝日が差し込んできて、驚いたこともあった。大学生になってからは、翻訳されていない小説を英語で読みたくなって、背伸びをして、辞書を引きながらペーパーバックを紐解いた。今となっては学生時代のような贅沢な時間の使い方は許されないが、基本的な生活は変わっていない。
英文科の学生だった頃、熱中していた作家はサリンジャー、フィッツジェラルド、カポーティ、マッカラーズである。不思議なことに、どんなに読書経験を重ねても、好きな作家は基本的に変わらない。むしろ年々彼らへの思いは熱くなるばかりで、とどまるところを知らない。彼らの生涯と、作品の特徴を無理矢理ひとことで今ふうにまとめると、ズバリ「青春こじらせ系」である。
サリンジャーは『ライ麦畑でつかまえて』の爆発的ヒットののち、半世紀以上いっさい公の場には顔を出さず、作品も発表せず、隠遁生活を続け、2010年に自宅で老衰のため亡くなった。「謎の作家」としてあまりにも有名である。フィッツジェラルドは1920年代に『グレート?ギャツビー』などで一躍売れっ子作家になったが、1930年代には人気は低迷、多額の借金を抱え、重度のアルコール中毒に陥り、44歳で亡くなっている。カポーティは20代前半で注目を浴びたが、晩年は薬物とアルコール漬けの日々を送っていた。マッカラーズもまた、波乱万丈の人生を送り、50歳で短い生涯を閉じた。
彼らはみな、あまりにも繊細で不器用すぎて、「上手に大人になれなかった」永遠の少年、少女だったのであり、まさにそれゆえ、世代を超えて今も世界中で愛読されている(マッカラーズは知名度が低いが、村上春樹氏の訳が近々登場することになっているようだ。彼女はカポーティと同時代の南部の女性作家で、訳書は絶版になっている)。修羅場に近い人生を送った作家たちの苦労は計り知れないが、これほど愛されれば元は取れるのではないか。
私自身、なぜ「青春こじらせ系」作家たちに引寄せられ続けるのか、その理由は自分でもわからない。もはや恋愛のようなものである。オトナになるにしたがって、背後に捨て去ってしまった、なにか大切なものを、彼らの小説は思い起こさせてくれる。私がサリンジャーの中で一番好きな小説は『フラニーとゾーイー』であるが、さきほど久々に本棚から出して頁をめくってみた。フラニーは『ライ麦』の主人公ホールデンの女子大生ヴァージョンである。純粋さゆえに周囲の若者たちにうまく馴染むことができず、煩悶するフラニー…。ページの間から漂う「こじらせ」臭がたまらず、私は一気に作品のなかに引き込まれ、フラニーと同化して、一緒に泣いたり笑ったりしてしまう。苦いような甘いような、複雑な思いを噛みしめながら。
青春時代が、みなにとって輝かしい世界で作られているとは限らない。
デリケートな若者の心のうずきを書かせたら、上記の作家たちはピカイチである。また眠れない夜を過ごすことになってしまいそうだ。