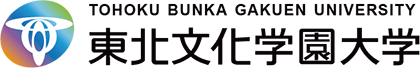国見夢物語(1)
総合政策学部教授 秡川信弘
「人類史における学校教育の意義とは何か?」地球とともに太陽の周りを廻る周回軌道を重ねすぎたせいか、近頃は時々そんな原点回帰の循環思考に陥ることがある。
明治26年(1893年)の夏、病み上がりの正岡子規は南山閣を目指して唸り坂を登っていた。そして、国見山からの眺望を「東ハ眺望豁然ト開キテ仙台ノ人 樹間二隠元シ、平洋碧色空際ニ模糊タリ」と詠ずる。青空に溶け込むかのごとき蒼い水平線を背景に、人々が木々の間に隠棲しているかのように見える杜の都仙台の原風景が彼の目前に広がっていたに違いない。
時の流れとともに変貌したのは市街の風景だけではなく、子規が踏みしめた山道もかつてのそれではない。だが、城下の人々の暮らしを支えた水源の森は、仙台市水道局が管理する浄水施設の設置場所として現在も21世紀の高度情報化社会を生きる人々の生活を支えている。125年前の昔と変わることのない天地自然の下、里山の大学から彼岸を眺めながら「楼閣ノ間ニ隠元スル」であろう125年後の人々のlife-styleを考えたい。
江戸時代、初代藩主政宗公が採択した環境保護(治山治水)政策の重点地区に指定された国見山はいわば現代の自然公園に相当する自然保護区として位置づけられていたと考えられる。とはいえ、その利用法には文字通り「隔世の感」がある。例えば、現在の自然公園は景観保全を主目的とする「自然公園法」に基づく利用規制がなされ、それが緩和された一部地域において林業やリクリエーションが行われているにすぎない。これに対し、江戸時代の国見山は「巻狩」という軍事訓練の場であり、江戸から戻った藩主が余暇を楽しむ狩猟場として庶民による利用は禁じられていた。さらに、鳥獣保護区としての現代の自然公園とは異なり、巻狩の獲物である鹿や猪などは武具(鹿皮など)、漢方薬(鹿茸など)、食料備蓄(乾肉など)に利用され、狩猟対象となる鹿の生息地であることを示す「御鹿籠山」の呼称も残されている。
だが、藩の軍事?警察力を背景に「鳥屋守」という自然保護官によって「生物多様性」が保全されていた国見山は江戸後期にはその様相を一変させたと考えられる。米本位制の経済基盤上に市場経済を発展させた幕藩体制の内在的矛盾は異常気象の頻発という不運もあって、宝暦、天明、天保期に深刻な飢饉をもたらし、水源?生物保全のために入山を制限した国見山も緊急避難的な飢饉対策としての御救山へと変貌していく。その痕跡は宅地造成のために崩された雷神社を祀った御山跡公園の石碑にも残されている。
さらに、維新後は欧米列強による植民地支配を防ぐための近代国家建設を急務とした政府の富国強兵政策(殖産興業および兵制?学制?税制改革)の下、人口増加に対応する主穀増産を担う農家の暮らしとともに、食料生産の場である農地=圃場生態系の再生産を支える薪炭?落葉及び刈敷の補給地として利用されてきた。藩政期、生命維持に不可欠な水資源(水源の森)として城下に暮らす人々の生活を支えた国見山は、現在もその末裔の暮らしを守る水道水源(浄水場)の設置場所としての役割を果たしている。
鹿ならぬ人の籠る住宅地やニュータウンに変貌した国見地区は時代の潮流に適応して変化し続けている。その来し方行く末を考え、里山文化の未来形を創出することもこの地にキャンパスを構える大学人の責務の一つではないだろうか。あらゆる地域社会がグローバル化や情報化の激流に呑み込まれようとしている今日、時代錯誤の誹りを免れることはできないだろうが、自然と調和するために求められる知恵や技術を尊重した時代の片鱗をこの地域の中から見出し、それらに学びながら里山文化の未来について考えていきたい。