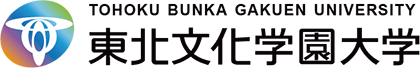国際社会における悲観と楽観
総合政策学部教授 永澤雄治
悲観と楽観といった二元論的な見方は、国際社会においても混在しているが、最近は悲観論が優勢のようだ。EUをめぐる議論でも例外ではない。昨年6月の国民投票による Brexit(英国のEU離脱)⑴の影響で、この1年は、EU崩壊を主張する論者が絶えない。おそらく意図的に単純化した見解を述べているのだろうが、そのような議論を目にするたびに不思議な気持ちになる。
思えばEUが共通通貨(Euro)を導入する前も、EU学会の中では悲観的な見方が支配的だった。シニカルな悲観論を提示しないとインテリっぽく見えないという恐れでもあったのだろうか。ギリシャの財政危機は、「政府が二重帳簿を作成!!」という稀有な事態が招いた結果であるが、その時もEuro崩壊論がやかましかった(ギリシャ問題は継続中だが、それよりもBrexitや右派勢力の台頭などで現在は以前ほど騒がれてはいない)。
東アジアに目を向ければ、ミサイル実験を繰り返す北朝鮮政府は、6回目の核実験も計画段階にあるだろう。仮に核実験が実施された場合、トランプ政権は軍事行動に出るのだろうか?それは不可能だ。軍事力で圧倒する米軍でさえ、第1撃能力のみで北朝鮮を無力化することはできない。韓国や日本の米軍基地や都市が報復攻撃の対象となる以上、武力行使は選択肢から外さざるを得ないのだ。
イラクやシリアと北朝鮮では全く状況が異なる。米政府もそんなことは認識済みだろう(特に陸軍出身のマクマスター大統領補佐官を始めとする安全保障担当官は)。武力行使が事実上不可能である中、空母や原子力潜水艦などを派遣しプレッシャーを与えているつもりが、逆に米政府が追い込まれているようにさえ見える。
北朝鮮政府は、米本土を射程に入れた長距離核ミサイルの開発に国家の命運をかけてきた。しかもこの核戦略は過去20年以上一貫しており、残念ながら国際社会は、北朝鮮の戦略を転換させるだけの決定的な影響力を持たない。国連による一連の制裁決議はもちろんだが、米政府の北朝鮮対話に向けたサインすらも効果がなかった。
同様に中国政府の圧力も効果的とはいえない状況だが、中国政府には有力なカードが残されている。石油と天然ガス供給だ。しかしこれが最強で最後のカードゆえに、供給制限の程度と時期について、中国政府も頭を悩ませているだろう。中国政府もまた追い込まれているのだ。
相次ぐテロ事件や紛争地帯で生じる悲惨な事象に目を向けると、21世紀の国際社会は暗い時代に移行しているように見えるかもしれない。シリアを逃れ隣国レバノンに避難している男性が、報道機関のインタビューに応え、「戦争はいずれ終わる。」と話し、帰国する希望を失っていなかった⑵。
1989年11月9日の深夜に、ベルリンの壁は意味を失った。どれほど強固に見える体制であっても、ある日突然、終わりを迎えるのである(当時、筆者は自分が生きている間にベルリンの壁が崩壊するとは全く予想していなかった⑶。歴史は劇的に変化することを、世界は目の当たりにしたのだ。
今から100年前は第1次大戦中だったことを思えばこそ、歴史を考える上で長期的視点を失ってはいけないのだ。100年単位で歴史を捉えつつ、目の前の現実を冷静に観察することが、悲観と楽観の二項対立を乗り越える思考方法なのだから。
注釈
⑴2017年3月末、EUに対し離脱を通知した英政府は、離脱条件をめぐり今月中にもEUと交渉を開始する予定である。順調に行けば、2年後の2019年4月に正式に離脱することになる。
⑵この男性が使っていた「戦争」という表現について補足すると、ロシアやアメリカを始めとする外国の軍隊が介入しているシリアの情勢は、国際政治学的に見ても内戦とはいえない。
⑶ベルリンの壁崩壊とそれに続く同年12月の米ソ首脳会談における冷戦終結宣言及び1991年12月のソ連邦崩壊という一連の出来事により、「冷戦は終結した」といわれている。しかし旧ソ連(ロシア)とアメリカ及びその同盟国間の軍事的緊張が解消されない限り、冷戦は終わったとはいえないだろう。ロシアがNATOに加盟した時に冷戦は本当の意味で終わるのだ。